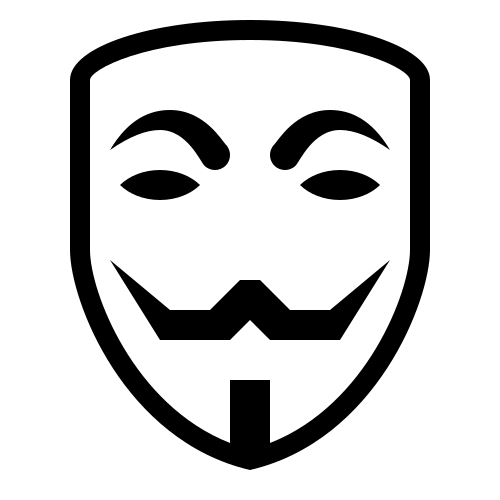“ケア”という響きに強さと脆さを感じる。「ケアすることで自分がケアされる」強さと「非対称の力関係」の脆さ。理学療法士(PT)の三好春樹さんは、「「介護」現場の目標は「臨床」ではなく「離床」にあるのだ」という(『共生から』P.76)。離床の意味は文字どおりかな。安楽病棟の人たちに離床はもらされたりするんだろうか。ケアを囲む離床の有無。私は「介護」を知らない。介護とケアの関係も知らない。安楽病棟にいる看護師はケアと口にする。介護という集合に含まれる要素のケアなのか、はたまた二つの独立集合が交わっているのか。読みながらつらつら思う。
一期一会、お招きした客人。主任さんが言ったその言葉は今でも耳に残っています。考えてみれば実にその通りです。旅先で人と巡り会ったり、あるいは仕事上で人と出会ったりするのと同じように、わたしたちは病棟で患者さんと出会うのです。まさしく一期一会に他なりません。それも頭ごなしに扱う患者さんではなく、招待する客人として接するのです。患者と思ってしまうと、もうそれ以上の何者でもない単色の人間になってしまいます。人であれば、色でたとえるなら赤黄青黒白という風に、ありとあらゆる色合いがあってしかるべきです。『安楽病棟』 P.460
安楽病棟の人の色は赤や青のひとつじゃない。歳を重ねた分だけ多様な色彩をおびている。ひとつの場面に十人いれば十人十色の反応を示す。それが日常生活ともなると多様性ははかりしれない。無限の反応がやってくる。看護のプロでさえ、その反応を十把一絡げにしてしてしまいかねない。目の前の人たちは患者になれば客人にもなる。一日のなかでも目がぐるしく変わる人たち。
ケアはたぶん日常のはず。なのに私は掬い取れなかった。ケアは非日常と日常の狭間なのかなと思ったり。
昨年、「あたりまえ」があたりまえでなくなった。そのときからケアがやってきた。同時に自分の無力を痛感した。ケアの脆さ。ケアする側とケアされる側の間に発生する非対称の存在。知識と情報。圧倒的だった。その非対称の存在を認めないと、ケアされる側は行為を優劣に置き換えてしまう。家族はケアする側とケアされる側を往来する。ケアする側のとき、「ケアすることで自分がケアされる」強さを感じ、ケアされる側のとき非対称の存在に圧倒された。家族でさえそう。だったらケアされる本人ってどんな気持ちなんだろう。それが頭にこびりついた。何もできない自分。主語を私にしていたらケアは私から遠ざかっていったみたい。
患者を病の悩みから解放し、病気が猛威をふるまうのを抑止するのが、医業の目的だったとヒポクラテスは述べている。これは常識であって、ほとんどの医師は心得ている。
しかし不幸にして患者が病気に打ち負かされたとき、治療にはもう手を染めない、ヒポクラテスはそのあとの文章で書いていて、これが大いに誤解を生んだーーーーー。『安楽病棟』 P.427
ヒポクラテスの誓いはDNR(=do not resuscitate)への曲解をもたらした。主治医がロボットのように論理の化け物であるならいざしらず、治療が無益かどうかの判断に医師個人の価値判断が混入する。純粋無垢な生理的判断はあり得ない。だからインフォームド・コンセントだと。情報と説明が跋扈する風潮。物事をはっきりさせれば、選択の幅が広がり自由であると主張する。だけど、物事をはっきりさせて論理の道筋をたどると、導き出される解は一つしかないなんて事実もある。その事実がもたらすのは失意。選択の自由が究極の束縛をもたらすかもしれない。
安楽病棟で起きる事件を小説の世界と一笑に付す、そんなことができるかなと経験と照らし合わせる。治療ではない患者、病棟に滞在するためのラベル。生の側から眺める終末期医療と死の側から眺める安楽死。ケアは生の側に存在する。ケアは死の側にも存在できないのか。死に至る処置を治療、あるいはケアの一種と考える。”先生”のそんな意見に家族として耳を傾けていたような気がする。主人公に己を投影して。
競走馬がレース中に脚を骨折するとどうなるか。マーシィ・キリング(慈悲ゆえの殺害)。馬の世界では当たり前。獣医学的にも論証できる。だけど、馬にしてみればどうか。
しかしね、実のところ、馬の生理からすれば、必ず殺さねばならぬことはないね。三本足で生きていけるからね。むしろそれを見て耐えられないのは人間のほうだろう。だからマーシィ・キリングをしてしまう。馬にしてみればいらぬお節介かもしれない。『安楽病棟』 P.624
馬にしてみればいらぬお節介かもしれないという見方。”かもしれない”という絶対的にわかりえない心理。そこへ”先生”は医師としてメスをいれた。死の側から論理と哲学と独自の情緒で。対して、主人公は「わからない」ままでいた。ケアの現場に身を置く、生の側から人間を眺めて。
私が安楽病棟にお世話になるとき、あるいは家族として見送るとき、いろんな立場を想像しながら答えのないケアをなんとしてもたぐりよせたくなった。