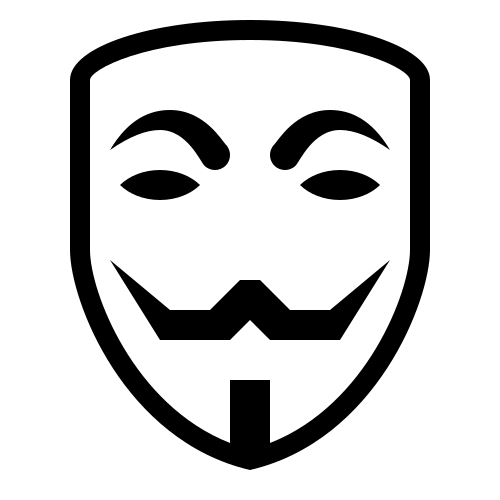「わたしってだれ?」「じぶんってなに?」と我に問うた。いつのころからこの問いを五臓六腑に置いたか。もうずいぶんむかし、覚えていない。きっかけが何だったかも忘れた。この問い、本書の冒頭にやってくる。
だれもがそういう爆弾のような問いを抱えている。爆弾のような、といったのは、この問いに囚われると、いままでせっかく積み上げ、塗り固めてきたことがみな、がらがら崩れだしそうな気がするからだ。あるいは、崩れるとまではいかないにしても、なにか二度と埋められないひびや亀裂が入ってしまいそうな気がするからだ。この問いには、問う者じしんをあやうくするところがある。
「この問い、どこか立てかたがまちがっているということはないだろうか」と鷲田先生は疑問を投げてくる。この問いを立てたとき、しばし「じぶん探し」が次にやってくる。読み手の私は「じぶん探し」に首をかしげる。
というのも、私は、「わたしってだれ?じぶんってなに?」という問いをもっているとはいえ、「じぶんを探した」経験を積んでいない(記憶の引き出しに閉じこめたのかもしれないけど)。「本当の<じぶん>」を発見できる「じぶん」は何なのか?
<じぶん>がわからないのに、「本当」や「本来」の<じぶん>とそうでない<じぶん>を判定できる<じぶん>は存在する。そんなことがあるのかと私は愚考する。だから、「じぶん探し」をしたことがない。いや、「じぶん探し」の仕方を私はまったく知らない。
「わたしたちはじぶんのからだについて、ごくわずかしなことしか知らない」と鷲田先生は言う。そうだなと納得する。冒頭の謎に出逢ったとき、私は<身体>にからだが震えた(妙な表現で恐縮)。鏡や飾り窓、水面や写真などに映るじぶんを除いたとき、私はじぶんの<身体>を見たことがない。
周りが、私だと認識している己の「顔」も見たことない。
さらに、意識。混乱の果てに突っ伏したくなる瞬間。<じぶん>をどこかに置いた「わたし」を意識したときも<じぶん>であるが、それを忘れている、無意識であるときの「わたし」も<じぶん>だ。どうかなりそう。
たとえば、からだをもたない<わたし>がありえないことはあまりに明白であるのに、それでは<わたし>と身体とはどのような関係にあるかと問うてみると、じぶんがほとんどなんの確かな答えももっていないことに気づかされる。
<わたし>と身体について明解を持ち得ていないのに、わたしは<じぶん>を”外”と区別する。ときに、ふつう一般とちがうかのように<じぶん>を隔離する。冒頭の問いを、私の”内”で解こうとするから。
私の姓名も私の顔も私の身体も…..それらは、他者が私を確認するためのラベルだ、と私は愚考する。そこになにやら神秘が宿っていたり、可能性を秘めていたりしない。
私と他者との間に、はっきりとわかる線を引き、その線の「私側」に<じぶん>の存在を隔離したとき、私は安心してしまう。その反対、線を引かず、わたしとわたしでない人との差異に生じる文脈から日々を検証したとき、強烈な不安が私に襲いかかる。
他者がじぶんとは異質なものとして一定のへだたりのなかで存在しているという単純な事実に直面したときも、その事実に耐えきれないで、他者をどうにかしてじぶんの理解のなかへ押し込め、じぶんの世界に同化させようとする。しかしそのようにしてわたしのまなざしの前に立つ他者は、観念化された虚構の「他」者であって、わたしがいままさに直面している問題としての他者ではないだろう。他者はもはやそこには存在しないのである。
冒頭の問いに囚われた私が<じぶん>を考察したくて読み始めた本書は、その後半、「他者」との関係を紡ぎ出し、最後におそろしい難問を提案する。
ほんとうに「他者」はいるのか?
「わたしが死ぬ」という経験をだれとも共有できない。自明の理。では、もし私が生きている間に経験する事象すらだれとも共有できないとしたら。
毎日私が目にして耳にする世界、私の眼前の風景を「じぶんだけのもの」と考えるひとはいない(私は断言できないけど)。にもかかわらず、他人が見たり触れたり思考する世界に私は原理的に近づけない。そもそもそういった世界があるのかどうかすら私にはわからない。
確証できない世界を、私は理解し、想像している。しかし、これは「わたしの世界」の内部にある。ということは、他者との接点は、「こちら側」からしかないのではないか。
にもかかわらず、「わたしだけの世界」ではなく「わたしたちの世界」とする。この世界は私の生死にかかわらず存在する「世界」。私の生死にかかわらず続く世界は、私を越えた「存在」である。「存在」が私の意識、私の経験のなかでなりたっている。ほんとうだろうか?
「自己というものを『他者の他者』」と規定した先生は、この難問に ジャック・デリダ のことばを引用する。
「<わたし>の宣言にはわたしの死が構造的に必然的である」
デリダは言う。「わたしがわたしじしんに向かって<わたしはある>と言うとき、これがわたしの不在においても理解可能であるのでなければ、言表としての地位ももたない。…..わたしが生きていようといまいと、<わたしはある>は意味作用をおこなう」P.172
デリダのこの一節に対して鷲田先生は峻烈なテキストを私に残した。先生ですら解けない問。本書の最後として締めくくられた問。私にはまったくわからない。
私が<じぶん>を掴む糸をようやくたぐり寄せてきたのに、その糸は無情にもプツンと音を立てて切れた。私が<じぶん>と向き合おうにも、私はまだまだ無知すぎた。