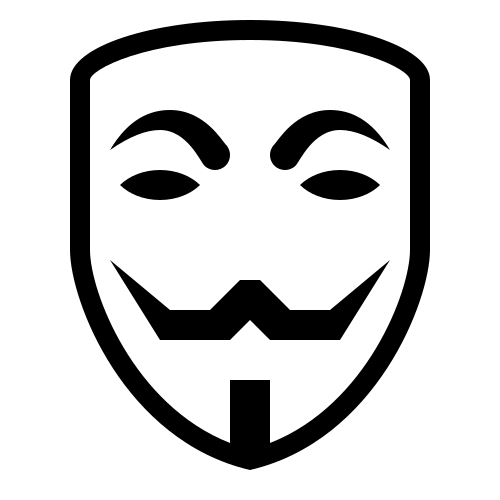ブログで本の感想を書き散らしていると、他の人が何を読んでいるのか気になる。やがて「どんな読み方」をしているのか読みたくなる。それが高じると作家や詩人が執筆した書評を読みたくなる。そして、『人に言えない習慣、罪深い愉しみ―読書中毒者の懺悔』 に出会った。
だいたい読書は、知識を深め情操を高めてくれる高級な趣味なんかじゃない。「ぼくを読んで」「わたしを見て」「ぼくのことを知って」「わたしだけを好きになって」と連呼する、自己中な連中の告白に耳をかたむけるのがなにより好き、ってなんかヘンではないだろうか?
本当のところ、本だけあれば外の世界でなにが起ころうが人間関係がどうなろうがどうだっていいと思っている(ぼくはそうです)なんてオカシきゃないだろうか?
御意。オカシイです。(ぼくもそうです)。知識を深め情操を高めてくれるわけなんてない。ただ活字が好きで好きで中毒になりたい(他の人に比べられると足下にもおよびませんが自己満足的に)から読んじゃう。それだけっすね。ただ、著者のようにどっぷりになれない。どうしても「読書」に棲んでいる人のことばが気になる。本だけあれば外の世界でなにが起ころうが人間関係がどうなろうがどうだっていいまで腹がくくれないわがままなやつと反省。だって、読書に棲んでいる人が口にするストックフレーズでないナマなことばを聴きたくてしょうがない。これが私の罪深い愉しみ。
ジャンルを限定せず「小説」をむさぼるように読んでいる筆者の姿を浮かび上がらせる。1冊につき2,3頁弱の書評。その内容は痛快だし、愛おしさが漂ってくる。踊るような文字にTPOで使い分ける文体。ポップにアバンギャルドな調子で、時に深淵を覗かせる。そのアップダウンが読む手を止めない。
<読者>である著者が書く文体に読者は引き寄せられる。ややもすると題材の本を読んだかのような錯覚に陥る。バカなオレとさらに反省。読者の読者という構造。どうしてこんな書評が書けるのだろう?
「良い読者」とは、(作者の)主人にも奴隷にもならない読者のことだ。「主人」とは、作者に向かって、面白いことを書け、と注文ばかりつけて自分ではなにもしない読者のことだ。「奴隷」とは、作者がなにを書こうと唯々諾々と受けいれる読者のことだ。そして同じように、「良い作家」もまた、(読者の)主人にも奴隷にもならない作者のことなのである。だが、なにより重要なものは、「良い読者」と「良い作家」は単独では存在できず、お互いを必要としていることだ。読者とは、読者と作者が織りなす、命懸けの共同作業ではなかったろうか。
自分は「良い読者」にはほど遠いし、ましてや「良い読者」なんてそもそも考えたことがなかった。この一文を読んだとき気づいた。(強引かもしれないけど)読者を自分の仕事に置き換えるとよくわかる。経営者(=作家)を支援するという立場。
先週の土曜日、営業の帰りに本書を読み終えたので、ことさらこの言葉が響いた。「良い読者」に気づいたとき、眼前に広大な視野がひろがる。主人にも奴隷にもならない。じゃぁ、どうすればいい? 葛藤がようやくはじまる。
それからはじまる「ゆらぎ」の中から「読者の読者」を引きつけることば生まれてくるのかな。また本を手にとって読んでみよう。