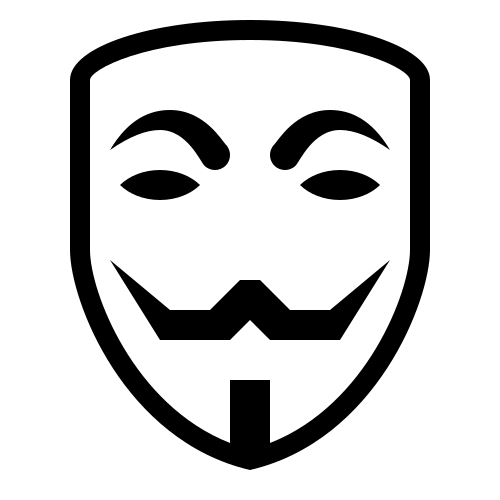自分にとっていちばんの死角は、自分の顔である。
日夜、他人に曝しておきながら、自分自身ではその顔を見ることができない。
鏡を使って確認することはできるが、それは「鏡像(左右が逆転している像)」であり、ほんとうの顔の左右が入れ替わった像に他ならない。試しに鏡像を反転させて「正像」をつって「鏡像」と見くらべてみればよくわかる。[…..]多くの人が自分の「正像」にはどうしても違和感を覚えるだろう。「いつもの自分ではない」と。それもそのはずだ。普段、見慣れている自分の顔は「鏡像」なのだから。
しかし、他人が見ているあなたは「 「正像」だ。「わたしが知っている自分とちょっと違った顔」を、他人はあなたの顔として識別しているのだ。“化粧する脳 (集英社新書 486G)” (茂木 健一郎) P.50-51
茂木健一郎先生の著書は同工異曲であっても読む。今回もそう予想して読み始めた。予想は見事にはずれた。良い感じ。どうしてはずれたか。それは、「化粧の本質」にある。先生の研究グループは、2007年7月からカネボウ化粧品と共同で脳科学的な知見から「化粧」を研究してきた。その結果をメンバーのひとりが本書で論文寄稿している。論文寄稿を起点にした論考だからか、同工異曲の濃度が薄いように感じた。
本書の論文で紹介された「化粧」の検証結果を興味深く読んだ。もちろん素人だから脳科学的な意味を理解できなかった。あくまで、自分の周りにある「化粧する女性」を想起して読んだにすぎない。それでもおもしろかった。そんな結果が出たのかと。
「化粧」は記号であって、「化粧された顔」は象徴だ、と僕はまとめた。そして、記号と象徴を信号として他者へ送信する。化粧はコミュニケーション能力の根幹であり、茂木健一郎先生は、コミュニケーション能力を人間の知性の本質と定義した。
化粧を顔にほどこす。顔は他者へ曝す心の窓口。鏡像と正像の差異。それは自分自身で判別できないほどの軽微。顔は常に見られている。私の顔を見る他者の顔を僕は伺う。言語化できないニュアンスを読み取る。他者の顔は私の顔を読み取った結果であり、原因でもある。原因と結果は融合され、いつしか融合すら忘れ、顔から伝達の根本をたぐりよせる。たぐり寄せられれば安心、たぐり寄せられなければ不安。顔は「祝福」であり、同時に「呪い」なのだ。
本書によると、人間の大脳新皮質のうち、約3分の1にあたる部分が視覚にかかわる領域らしい。人間は視覚優位の進化をとげてきた。視覚に依存しすぎているとも考えられる。視覚は「見る」という欲望を生み、顔は「見られる」という欲望を生む。
しかし、僕は顔を見ているだろうか。「見る」という欲望に身をまかせ、視覚に依存する毎日にかまけて、実は見ていない。一体何を見ているのか。否、本質は目には見えない。
顔は美の判定基準に組み込まれれる。エロスのとば口。では美は何か。化粧する顔から先生は美へと論考を深める。顔の美についても興味深い実験結果を提示している。見える美と見えない美の本質。
「化粧」を顔にほどこす行動だけと捉えたら、秘められている意味へ永遠に辿り着けない。なぜなら、「化粧」は顔だけにするものではない。
「化粧」という意味、それは、「言葉を化粧する」と書けば、理解へのスタートラインに立てるかもしれない。
茂木健一郎先生はブレインという名称のヴィークルに僕を乗せ、化粧された「顔」から「共感感覚」と「美」への道を走り、それから「言葉」へハンドルを切り、そして、人間の知性へ案内した。
素敵なドライブだった。
[ad#ad-1]