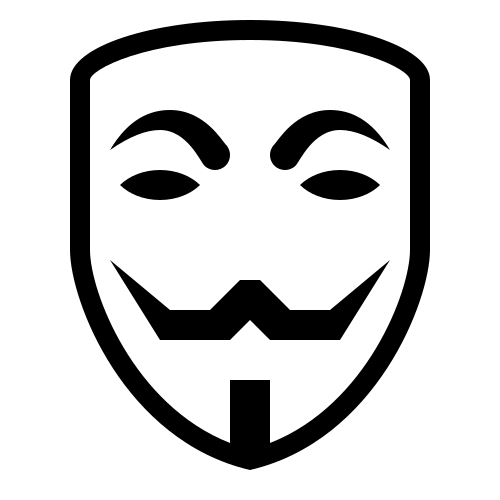“シンプル”ということについて原氏は、「シンプルの品質は思考の総量が決める。ただ単純なのではない。同じシンプルでも、考え抜かれたシンプルかどうかが重要」という。幾何学的に簡素であるというだけではなく、それが「多様なイメージを一身に受けとめられる容量の大きな器として機能するかどうか」。優れたシンプルは懐が広い。どんなイメージも受け入れる。それは単に省略するとかデザインしないということとは、全く逆のベクトル上にある。つまり、考え抜いた果てでないと、品質のいいシンプルにたどり着けないということだ。
「ブランドのデザイン」を知りたくて買ったのではなく、原氏のインタビュー(P.254-257)を手元に置いときたくて購入した。ほんの少しだけ気持ちが安定した。シンプルの意味を誤解していなくてよかった。大きくはずしていなかった。
広告は日常生活に溢れている。目に止めるコピーや素通りされるポスター、何となく気になる形や色、思わず画面を見直すCM、まったく目を引かない雑誌のページなどなど。その中でロングセラーを続ける商品は必ず存在する。
伊右衛門の形は、「日本人の心と手に最もなじむ竹筒のかたち」を象ったものだから、自動販売機に入らず物議を醸した。商品開発が短サイクル化している飲料市場で、4年の歳月をかけて議論されてきた。「ブランドをどう伝えるか」までを戦略に組み込むこと自体が、サントリーでは異例だったとの由。
25年以上売れ続けているサントリーのウーロン茶は競合が登場しても「ほっておくに限る」と構えて自分たちの哲学を洗練させてきた。
キューピーマヨネーズは、「良質で栄養価の高いものを行き渡らせたい」という信念で支えられ、「どんな時代にも変えてはいけないことを守り続け」ながら「どんどん工夫して」いき、進化させてきた。
年間500億円の売上を誇る資生堂の「クレ・ド・ポー ボーテ」は、ただ販売しているだけじゃない。販売の「前後」も含めて「最高品質」を築き上げている。「物事はすべてリッチでなければならない」という初代社長のフレーズが商品に込められ、「世界で通用する」品質を広告で伝える。
日常生活で何気なく手に取る商品や積極的に買う商品。自分の感性に響いたから買う商品や何となく買ってしまった商品。長きにわたって人々の手に渡ってきた商品や世界を変えるような商品には、物語がある。創業者や経営者の人間性が垣間見られる。伝統と革新の両方を持っている。技術が蓄積されている。
だけど、僕はそんな「ブランドの要件」を知り抜いて買っているわけじゃない。広告はそんな僕へ「伝える」役割を果たしている。どうやって伝えるのか、という発狂しかねない激論をくぐって、「メッセージ」は伝えられる。伝え方や表現、言葉、映像、ありとあらゆる送受信の確立を模索する。
今、周りに耳をかざせば、「あたりまえ」のことをレトリックやボディーランゲージでカッコよくまとめて、「さもありなん」とする喧噪が聞こえる。どれももっとも”らしい”ことを言っているにすぎない。思考の総量が少ない。
心に響く広告は、「あたりまえ」をカッコよく語らない。朴訥として、たとえコピーであっても、少しひっかかりながらしゃべっているような、「これがいい」じゃなくて「これでいい」ような意志の強い控え目なふるまいに満ちた言葉で彩られている。
あたりまえのことを自己主張する。簡単だ。だけど、あたりまえの背後に隠れている逆理を「視点」として気づかせるような伝え方。
主張は説得に変わり、いつしか説教となる。気づきは認識へ変わり、いつしか理解へ昇華する。そんなふうに僕は今考え始めた。沈黙していきたい。雄弁に語りたくない。時間と仲好しになって、気づきを待ちたい。
読みながらそうワクワクした。
[ad#ad-1]