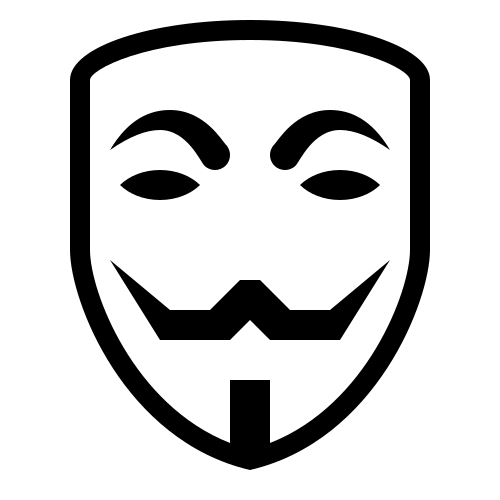たとえば、「子供に夢を与える」と言いながら、本当に夢を見る者を徹底的に排斥しようとする社会。集団はいったい何を恐れているのだろう。多くの大人たちは怯えて何もできない。ただ作業をするだけ、子供を育てるだけ。新しい目的に挑戦している者は少数である。それなのに、子供には挑戦させようとする。自分たちにはとうてい消化できないものを子供に与えている。こんな動物は他にいるだろうか? 『夏のレプリカ―REPLACEABLE SUMMER』 P.14-15
「人のせいにしてはいけません」と子供のときに叱られた。「他人に迷惑をかけていけません」と子供のときに諭された。「謝りなさい」と子供のときに教えられた。大人の言葉は正しいのだろう。だけど「正しい」は世の移ろい。言葉の意味は認識する人によって変わる。「正しい」と発声した途端、言葉の内側に包まれる「正しい」は外側に広がる「わからない」を対象から隠す。内側と外側の境界に「間違っている」が囲っている。
「人のせいにしてはいけません」と言った大人は、「社会のせいにしていけません」と言わない(ゼロじゃない、断定調に自己陶酔)。それどころか「社会のせい」にしたがる人もいるぐらい。不思議だ。「人」と「社会」を使い分ける。社会は表象しづらいから制度に置き換えたり。制度も腑に落ちないなら公務員、政治家、官僚、経営者…..。集合の範囲を狭める。抽象から限定へ。限定はラベルにすぎない。「人のせいにしてはいけません」の人が構成する仕組みの名称だ。名称なら「せい」にできる。実害はない。
「正しい」の外側にある「わからない」を認識しようとしない。恐い。恐いから「何かのせい」にしたい。したいけど「人のせいにしてはいけません」という「正しい」がある。大人が「正しい」を言った。大人が言った「正しい」は彷徨い、すべての「正しい」が子供たちへふりそそぐ。そして大人は「正しい」を忘れる。自分が言った「正しい」だけを残して。