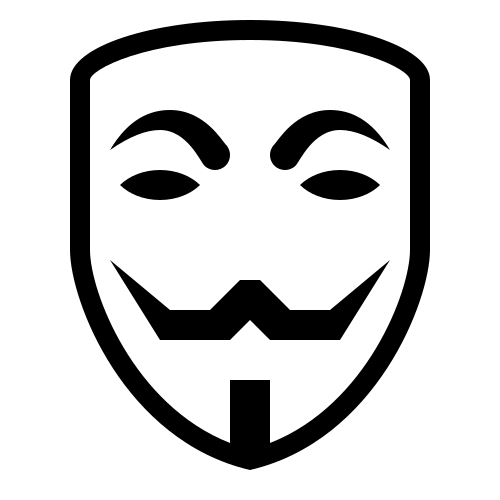前作、『他人と深く関わらずに生きるには』と比べても内容に大差はない。ただ、いくぶん受ける印象が変わった。理由は前景に思想がおかれたから。前作は後景に思想があった。思想を前景か後景のどちらに描くかは、作品の仕上がりに影響を与える。こうも様変わりするとすこしばかりのけぞった。前景化された思想を原理主義に染めないようにコントロールするのは難しい。その手綱さばきを味わえる一冊。
じゃ、何が書いてあるかって。善く生きるための原理が書いてあるのだ。原理といったって別に難しいことじゃないよ。善く生きるやり方は人によって様々だし、同じ人だって、状況によって変わることもある。[…]この原理をひとことで説明することはできない。ひとことで説明できるのなら本を書く必要なんてないからね。でも、あえて言えば、自分なりの規範を決める、ということかな。
池田清彦先生は「自分なりの規範」という。私はこれを規矩と読む(正解かどうかはわからない)。自分なりの規範は道徳や倫理と違う。道徳や倫理は他人が決めた規範だ。本書のいう規範はあなたが決める。
前作同様、第一部と第二部から組み立てられている。第一部には善く生きるための原理がまとめられている。対偶で考える。つまり他人が決める規範の道徳や倫理、法律をどう解釈するか。先生は、それらを「欲望を調停するための道具なのである」という。ところがヒトは目的と道具をときおりひっくり返す。ひっくり返ると、「道徳や倫理を守ることが社会の目的」となる。それはおかしい。だから異を唱える。
その異が第二部につづく。まずは、「既成の道徳や倫理をとりあえず無視して、どういう調停を行えばよいか」を先生が提示する。自分の欲望と他人の欲望をどのように調整するか。その調整を問うのが正しい生き方であり、善く生きることの原理となる。それらは個人に帰結する。そして、「自分なりの規範を決めること」が導出したのはリバタリアニズム。それが本書の体幹だ。
私の依って立つ原理は極めて単純で、次のようなものだ。
「人々が自分の欲望を解放する自由(これを恣意性の権利と呼ぼう)は、他人の恣意性の権利を不可避に侵害しない限り、保護されねばならない。但し、恣意性の権利は能動的なものに限られる」
恣意性の権利は能動的なものに限られる。他人を愛する権利を有しても他人から愛される権利はない。ただし、この原理の前提には、「人々は原則的に平等である」との公準がある。人々は原則的に平等であり、かつそれぞれの恣意性の権利を保護するために、人々の欲望の調整をどうするのか。それを実現するための制度はどうあるべきか。それらの問いに解をだす。
世の中は多様だ。国内に限定しても多様であり、ひとたび国外に目をむけると言語・文化・宗教・伝統・民族などキリがない。かといって、すべてを「白紙」にもどせない。だから複雑な多様性に至極簡単な原理を先生は提示した。複雑を超えて共有できうる(であろう)明快な理路。
仮に先生の依って立つ原理を肯定できたとしよう。だが、その次の様相に合意できるとはかぎらない。それでもひとつひとつについて弁証を積み重ねる。この作業がヒトに与えられた能力だと私は思う。気の遠くなるような道のりを膨大な言葉にのって探索する。それはじぶんがいる間に解決できるようなシロモノではない。それに耐える我慢を強いられる。あきらめたくなる。たかが一人で何ができると罵り、でもやっぱり一人が何かをはじめなくては波紋にならないと前を向く。そうやって先人は叡智を残してきた。
先生の「理想状態における理論や制度」は独創ではない。はるかむかしから闘争と淘汰、時代のフィルターに濾過されてきた。私には、それらを批判する力や反証する知性、補筆する知識もない。そのかわり、ずっと考えつづけたい「問い」を与えてもらった。ただそれだけである。
最後に、国家のパターナリズムについて一言。私の考えによれば、人は自分で自分の規範を選び、他人の自由を妨げない限りにおいて自由に生きる権利がある。封建時代ならばともかく、単一の生活規範を国民に押しつけようとする考えはもはやうまく機能しないばかりではなく、様々な価値観をもつ人々が共生しなければならない国際社会において、むしろ有害なのだ。人は必要最小限のルールを守れば充分であり、国家が教育により何らかの価値観を押しつける必要な全くないのだ。制度は人々の平等を保証すると共に、人々の選択を最大限許容するものでなければならない。倫理や道徳の押しつけは不必要であるばかりでなく、正義の観点からは悪である。『正しく生きるとはどういうことか』 P.153 “平等というフィクション”より
「人々は原則的に平等である」との公準を考察した中に登場する文脈。これがむなしく響くのか奮い立たせるのか、はたまた胸くそ悪いか、それは読み手の多様だろう。
現実が我を覚醒させたとき、このくだりに嘲笑する自分、何も反論できない自分、その自分に嫌気がさす自分、あきらめない自分、無関心な自分、それぞれがじぶんのなかで共存している。
そう思いながら読み進めたとき、「あとがき」のあるくだりにユートピアを具現するスタートラインがあると確信した。それは、「あとがき」を書く先生の耳に四方八方からささやく「もう一人の私」である。