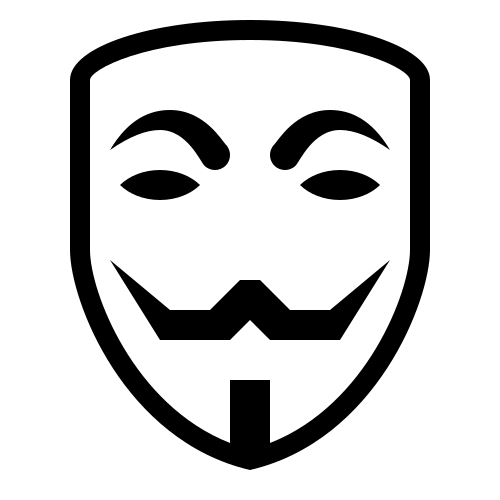ことばはいつもちぐはぐだ。いつも過剰、いつも過少。ことばはそうしたずれを孕んだままでやりとりされる。充足したコミュニケーションなどというものは思ってみたこともない。だが、ことばを表現とか記号というふうにかんがえずに、ふるまいや身ぶりだとかんがえれば、ことばのちがった面も見えてくる。手を差しのべる、ちょっかいを出す、吐き棄てる、歌う、啼く、呟く、遊ぶ、懐深く受けとめる…..。ことばの<顔>というのが気になりだしたのはそれからだ。
『ことばの顔 (中公文庫)』 鷲田 清一 P.283
その<顔>について執筆した断片を一冊にまとめた。ことばを表現として考想せず、ことばにふるまいを挿入して論考する。五感を味わうための<ことば>が目に飛び込んでくる。
鷲田先生の著書を読むと(哲学論考をのぞく、まったくわからないので)、「ことばを粗末にあつかっているなぁ」と自省する。いや、粗末にあつかうというのも的確ではない。あつかいすらできず、口から吐きだしているにすぎない。うなだれる。ことばに対して鈍い。
ことばに対して鈍いじぶんを認識したとき、ようやく、<ことば>に向き合える。皮肉にも、向き合ったとたん、言葉を失う。他者への恐怖が芽生える。それを身にまとい、己との対話がはじまる。言葉なき思考。「どうやって考えるのか」という問いからはじまり、その考えるためのことばを持っていないじぶんに気づく。愕然。こんどは己にも恐怖する。そんな愚行を先生は強烈に叩いてくれる。
わたしはわたしを「自我」などと言って、すました顔をしていられるのかということである。「自我」などと言って論じた気になったとき、わたしがわたし自身にくわえる変形の過程は、問題として隠されてしまうことになる。問われているわたしが、わたしの論述のただの一対象にすりかわってしまうのである。じぶんがじぶん自身にかかわるそのあり方が問題とされながら、それがすっぽり脱落して、わたしは他人事のようにわたしについて語りだすのである。これはもはやわたしについて語ることではない。これはもはや「哲学」ではない。
『ことばの顔 (中公文庫)』 鷲田 清一 P.209
わたしについてわたしが語るとき、「限定するわたし」と「限定されたわたし」が表出する。表出した両者の関係についてさらに言葉をくわえる。これがわたしについてわたしが語るとするなら、それは、「限定するわたし」と「限定されたわたし」の関係をさらに別のかたちで限定することである。
三重に限定されたわたし。限定を積み重ね、メタ次元から限定へ介入する。限定とは、あるものを変形すること。わたしがわたしを語るというのは、変形に変形をくわえるわけで、その変形の「やり方自体」を問うのが「哲学」となる。その問いは、緻密であり、論理であり、ときに倫理でもある。
言葉をもってして何かを考え、語り出す。すると、語り出した事態を言葉は正しくとらえているかを問う。「語り」と「語られる事態」の一致と不一致を問う。しかし、その一致と不一致を問う<何か>は何か。ここに哲学の陥穽がある。
その<何か>を無理にことばをつくりだそうとして、<自我>は難解な解釈をうみだした。タームと化した言葉。わたしが考えるのではない。<自我>が考えている。その<自我>はわたしを語らず。言葉なき愚考、他者になりえない他人事である。<自我>という鵺がひとり歩きする。
<自我>ではなくわたしがわたしを語るとは、造語や難解な言葉をつかわずに自分が咀嚼できることばで考えることである。ほんとうなら哲学は、だれもが日常使っている言葉が問いただされているわけで、それによって語れる文章をだれでも読めるはずだ。
そういう視座に立つ本書は、ことばを起点に実体の言葉を観念の思考へとのばしていく。そして、実体の言葉へとふたたびちぢむ。
その伸縮する様がことばの<顔>だと私は思う。ことばそのものが実体と観念を往来するのではなく、ことばを覆う五感が、私と他者をつなぐ架け橋ではないか。
手前味噌だけど、かつて経営者から経営の悩みを相談されるような仕事にたずさわっていた。そのとき、訳知り顔で「コミュニケーション」を語っていた。今から考えると顔から火がでるほど恥ずかしいし、無知を自覚していなかったからこそふるまえたのだろう。
あのときの私は「コミュニケーション」を他人事のように語っていたのだろう。わたしがわたしを語るとき、<自我>がわたしを語るように。哲学を解説する難解な用語と同様、「コミュニケーション」を「それはコミュニケーションの問題ですね」とかろやかに微笑んでいた。
その無知を自覚したとき、私はその仕事から足を洗った。いや逃げた。私ごときが勤まるシロモノではなかった。
理解するということは、じぶんと他人が同じ存在ではないということを思い知ったところから始まる。<理解>とは同じ気持ちになること、コンセンサスを得ることではない。むしろじぶんと相手のあいだにある深い溝に気づくこと、他人のみならずじぶん自身との関係においても言葉の無力に深く傷つくこと、ここから<理解>への言葉と沈黙によるたどたどしい歩みが始まる。
『ことばの顔 (中公文庫)』 鷲田 清一 P.226
皮肉なことに、逃げたてからようやく「たどたどしい歩み」とスタートラインに立った。